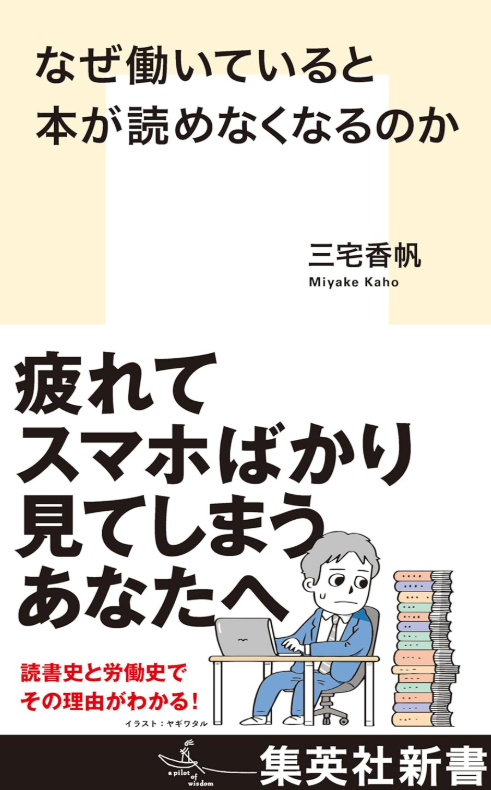おはようございます。こんにちは。こんばんは!
どうも、ぽめおです。
今回は、三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』をご紹介します。
「本が読めない」──それって、意志の弱さのせい?
行き帰りの通勤電車。本を読みたい気持ちはあるのに、気づけばスマホでXを眺めたり、ゲームアプリを開いたりしている。
「時間はあるのに、なぜか読めない…」そんな体験、ありませんか?
かくいう僕自身も、バッグにKindleは入ってるのに、通勤時間につい『ポケポケ』を開いてしまう日々。
ゲームはできるのに、本を読むと言葉が頭に入ってこない。
「自分の集中力がないだけなのか?」
「意志が弱いからダメなんだろうか…」
そんな自己嫌悪に陥っていたとき、Xでフォロワーさんがこの本の読了報告をしていて、「そうだ、これだ!」と思って手に取りました。
Q.なぜ働いていると本が読めなくなるのか?どうすれば本が読めるようになるのか?
A.現代社会において「読書」が“ノイズ”として扱われるから。
過剰な自己搾取をやめて、「半身社会」を生きていくことが必要。
目次
What:「本も読めない社会」とは何か?「ノイズ」とは?
ここでの「読書」とは、必ずしも「本を読むこと」ではなく、「家族でゆっくり過ごすこと」や「趣味の映画を観ること」など、「仕事以外で自分がやりたいこと」を指しています。
なので、読書が趣味ではない人は、読書を他の趣味に置き換えて、「なぜ働いていると〇〇ができないんだろう」という問いに対する答えがあるかもしれません。
著者の三宅さんは、本書の中で前提をこう指摘しています。
この社会は、『自己実現=仕事』という価値観でできている。そしてそれは“良いこと”とされている
この前提に立つと、仕事以外の活動(たとえば読書や趣味、休息)は「非生産的なもの」と見なされてしまう。
つまり、“仕事以外”の活動は、どこか「後ろめたさ」を伴うものになってしまっているのです。
本書ではそんな社会を「本も読めない社会」と表現します。
また、読書そのものも「ノイズ」として扱われています。ここでの「ノイズ」は、「自分が今直面している“仕事”の問題解決には直接関係しない情報」としてのノイズです。
そのため、「仕事にすぐ役立たないもの」ができない社会ができあがってしまうわけですね。
- 本を読む=自分の今とは無関係な情報を取り入れること
- 社会は「今すぐ成果が出ること」「わかりやすい行動」を求めてくる
- 読書は“効率が悪く、成果が見えづらいノイズ”とみなされてしまう
「自分の“今”に必要のない情報を遮断することで、私たちは働く社会に適応している。でもその結果として、ノイズとしての読書が排除されていく」
──つまり、読書とは「今すぐ役立つわけじゃない余計なもの」=ノイズ。
でも本来はそのノイズこそが、人生に深みを与えたり、自分を豊かにしたりする“余白”なのかもしれません。
Why:なぜ労働と読書は両立し得ないのか?
そもそも 読書の醍醐味は「知らない世界との出会い」 にあります。
つまり教養とは、「今の自分から遠く離れたところにある“異物”に触れる」ことで育まれることになります。
そのため、教養は予測できない偶然の出会い――自分の興味の外側にある出来事や考え――を受けとめることでしか手に入りません。ところが現代の情報環境は、アルゴリズムによって 「欲しい情報だけが自動的にカスタマイズされる世界」 へと急速に傾いています。
- ほしい情報だけを検索し、
- タイムラインは自分の関心事で最適化され、
- “今すぐ役立つ”ノウハウが歓迎される。
この効率至上の風潮の中では、役立つかどうか分からない“ノイズ”としての読書は後回しにされがちです。「偶然の出会いは、しばしばすぐには役立たない。だからこそ人をゆっくり豊かにする」わけです。
ところが、仕事で常に成果を求められ “もっとできる” と自己実現を強いられる私たちには、その“ゆっくり”に耐える余裕がありません。
加えて、スマホでSNSやゲームだけはなぜか続けられる問題。
本書はその理由を「コントローラブルだから」と喝破します。SNSのタイムラインやゲームのルールは、自分の予測範囲内で進行し、未知のノイズが入ってこない。だから疲れていても頭を使わずに済む。
しかし、本は違います。ページをめくるたびに、自分がコントロールできない他者の思考や未知の概念が流れ込んでくる。
要するに、
- ノイズだらけの読書 にはエネルギーがいる。
- 成果を急ぐ社会 はそのエネルギーを奪う。
- 余裕がなくなるほど、人は“予測可能で安心な娯楽” (スマホ)に逃避する。
だからこそ、働いているとスマホは触れるのに本は読めない――ということになるのです。
How:どうすれば、また本が読めるようになるのか?
本を読む時間を確保するには、単にスケジュールを空けるだけでは不十分です。
大切なのは“全身全霊”をかけて働くことが美徳とされる社会の空気から、一度距離をとることです。
たとえば、
「遅くまで仕事をしている自分は偉い」
「人より頑張っていることが価値になる」
といった価値観は、知らず知らずのうちに私たちの中に刷り込まれています。
しかしこれらは、自己搾取を促し、心と体の余裕を奪っていくものでもあります。
当然、仕事に全力を注がなければならない時期もあるでしょう。
それ自体が悪いのではなく、問題はその状態が“常態化”してしまうこと。
これが常態化することにより、「鬱病」や「燃え尽き症候群」といった不調を招いてしまいます。
こんな社会でも本を読むために、三宅さんが提案するのは、「半身社会」での生き方。
つまり――
全身ではなく、あえて“半分の力”で社会と関わり、
残りの半分は自分の人生に向けるという生き方をする
ということです。
このように心と身体に余裕を取り戻すことが、
本を手に取る気力を生み、「ノイズを楽しむ力」を取り戻す第一歩になると筆者は述べています。
「本が読めない」のではなく、「読める状態を社会が奪っている」ことが最大の悪です。
だからこそ意識的に“全身全霊”から一歩引き、「半身」で働くという選択肢を持つこと。
それが、再び読書と出会うための鍵になると本書は教えてくれます。
ぽめお的感想
本書を読んで、自分自身が「読書ができないのは意思が弱いからだ」と思っていたことが、まったくの見当違いだったことに気づかされました。
通勤時間、Kindleはカバンに入っているのに、ついスマホでSNSやゲームばかり…。
「疲れているから」「集中力がないから」と自分を責めていたけど、それ以前に、本を読むという行為が“ノイズを許容する余裕”を必要とする行為だったと知って、深く納得しました。
そして改めて感じたのは、「半身社会」で生きていくためには、心と身体の余裕だけでなく、“お金の余裕”も必要不可欠だということです。
「お金のために働かざるを得ない」状態が続く限り、どれだけ気持ちにゆとりを持とうとしても、読書のような“ノイズに身を委ねる行為”に手が伸びなくなるのも当然です。
だからこそ、“お金のための労働”から早期に卒業すること。
これが「半身社会」で生きるために必要な入り口であり、読書や趣味、家族との時間といった自分の人生をちゃんと取り戻す第一歩なのだと思いました。
このままでは、本を読むという豊かな時間が永遠に「時間はあるのにできないもの」になってしまう。
だから僕自身、仕組みを変えていく。
そのためにも、読書の良さと「半身社会」を実践する大切さを、自分の言葉で発信し続けていきたいと思いました。
▼最後に
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
このブログで紹介した書籍はこちらから購入できます📚
もしこの記事を読んで、「自分も同じようなことを感じていた」「もっと詳しく知りたい」と思った方がいれば、ぜひ一度、本書を手に取ってみてください。
日々の働き方や、自分の時間との向き合い方を見つめ直す、良いきっかけになる一冊です。
ご感想や、読後の気づきなどあればぜひXで教えてください。
それではまた次回の記事でお会いしましょう!