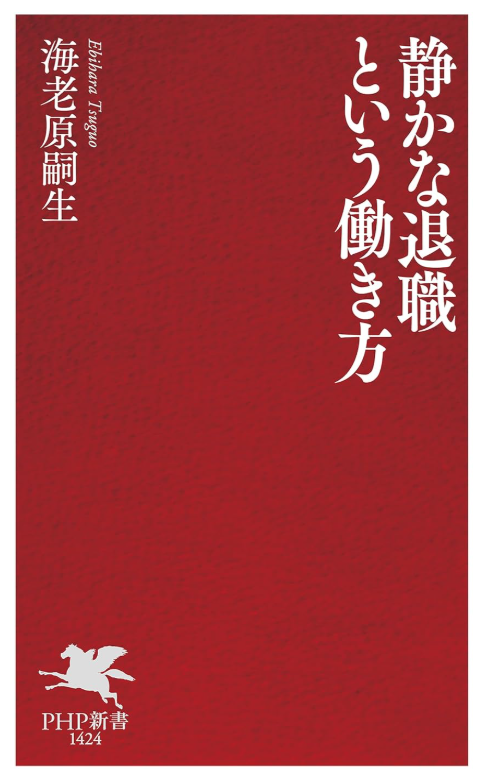こんにちは、あるいはこんばんは。ぽめおです。
今回は、海老原嗣生さんの新刊『静かな退職という働き方』をご紹介します。
いま話題の「静かな退職」って、何?
最近、Z世代を中心に「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を耳にすることが増えました。TikTokやYouTubeで話題となったこの考え方は、会社を辞めずに“必要以上に頑張らない”働き方を意味します。
“I’m not quitting my job. I’m quitting the idea of going above and beyond.”
(私は仕事を辞めるんじゃない。“必要以上に頑張る”という考えを辞めるの)
この言葉が象徴するように、いま働き方は「がむしゃら」から「持続可能」へと変わろうとしています。
それではいつも通り、今回も自分なりの結論から。
Q.「静かな退職」はなぜ昨今若者を中心に注目されているのか?その方法とは?
A.プライベートを重視したいという現代の考え方と、報われない社会への警鐘のマッチ。 働き方は「もっと頑張る」からの脱却。
今回は…
What:「静かな退職」とは何か?
Why:なぜ今「静かな退職」が注目されているのか
How:どのように「静かな退職」を実現するか
ぽめお的感想
この4つの観点から紐解いていきたいと思います。
ぜひ今回も最後までお付き合いください!
目次
What:「静かな退職」とは何か?
「静かな退職」とは、会社を辞めるのではなく、最低限の職務だけをこなしてそれ以上は引き受けない働き方です。
▼ たとえばこんな働き方
- 残業はしない(定時退社)
- 指示されたことだけを丁寧にこなす
- 出世や昇進を積極的には目指さない
- 熱意や情熱を仕事に全振りしない
誤解されがちですが、これは「やる気がない」のではなく、「やりすぎない」と決めているだけ。
▼「窓際族」との違い
日本にも「窓際族(窓際社員)」という言葉があります。一見すると、「静かな退職」と同じく“積極的に仕事をしない”という点で似ているように思えます。
しかし、その背景や意味は大きく異なります。
| 静かな退職 | 窓際族 | |
|---|---|---|
| 行動の主体 | 本人が選ぶ | 会社に決められる |
| 理由 | 自ら“やりすぎない”と決めた | 組織の都合で重要な仕事を 外された |
| 仕事への姿勢 | 必要最低限は責任を持つ | 仕事自体を与えられていない |
「静かな退職」は、自分の意志で仕事との距離感を調整し、自分の時間や価値観を守るための選択です。一方で「窓際族」は、会社から「戦力外」とされ、望まぬかたちで業務から外される状態です。
つまり、両者は見た目の行動が似ていても、能動か受動かという決定的な違いがあります。
「静かな退職」は主体的な選択です。キャリアをコントロールする一手でもあります。
Why:なぜ今、「静かな退職」が注目されているのか?
「静かな退職」は単なる流行ではなく、社会構造の変化と個人の意識の変化が重なって生まれた現象です。
▼ 社会背景にこんな変化があった
- 働き方改革(2019年~):長時間労働やサービス残業が見直され、「働けば評価される」という幻想が薄れた
- コロナ禍とリモートワークの普及:通勤が不要になったことで、時間や生活のゆとりを再認識
- 終身雇用の崩壊:「頑張れば報われる」「年功序列で昇進できる」といった前提が成り立たなくなった
これらの変化を通じて、多くの人が「仕事にすべてを捧げる人生って、本当に幸せなのか?」と問い始めました。
▼ 価値観の変化:人生の“主役”が会社から自分へ
特に若い世代は、上の世代のように身を削って働いた結果、心身を壊してしまった人たちを身近で見てきています。
そのため、「頑張っても必ずしも報われるとは限らない」という現実に対して、冷静かつシビアな視点を持つようになってきました。
結果として、「ほどほどに働き、生活を楽しむ」「自分の時間を確保する」という選択肢が、合理的で賢明な生き方として支持されるようになったのです。
▼ SNSでの共感の連鎖
さらにSNSの影響も大きく、X(旧Twitter)やTikTokなどでは、「静かな退職」を実践する人々の声が拡散され、共感や“いいね”を通じて広がっています。
自分の違和感や生きづらさが言語化された投稿を見ることで、「自分だけじゃなかった」と安心し、“静かな退職”という考え方に共鳴する人が増えているのです。
こうした環境の変化や情報共有のしやすさが、「静かな退職」が社会的に注目される大きな要因になっていると言えるでしょう。
How:日本型雇用の中で実践するには?
欧米では「ジョブ型雇用」が主流ですが、日本では「メンバーシップ型雇用」が一般的。
だからこそ、やりすぎない働き方をするには少し工夫が必要です。
▼ 実践のための7つのポイント
- 基本マナーを守る(服装・言葉遣い・報連相)
- ミッションは丁寧に遂行(最低限+αの信頼確保)
- 社内評価で下位2割に入らない(致命傷を避ける)
- 「自分の仕事の境界線」を定義(無理な業務は受けない)
- エネルギーの再配分(副業・発信・スキルアップに一部投資)
- 「できません」と言えるようにする(再配分や改善提案とセット)
- “静かなプロフェッショナリズム”を持つ(自分だけ楽しない)
「手を抜く」のではなく、“燃え尽きない働き方”を選ぶという考え方です。
ぽめお的感想
「静かな退職」という考え方は、欧米ではすでに広く浸透しています。誰もが自分に与えられた役割の範囲で、必要最低限の業務をしっかり果たす──それがプロフェッショナリズムであり、ワークライフバランスを重視した健全な働き方として受け入れられています。
これは自分が一番やりやすい働き方だと感じました。
背景にあるのは、欧米型の「ジョブ型雇用」です。これは、職務内容が明確に定義され、その“ジョブ”を遂行することが契約上の義務とされています。つまり、ジョブを果たしていれば、それ以上の仕事を求められることはありません。
一方、日本では「メンバーシップ型雇用」が主流です。これは、職務が明確に限定されておらず、配属や業務内容も会社側の裁量で決められます。結果として、“最低限”のラインが曖昧になり、「できる人がやる」「空気を読んで動く」ことが暗黙の期待として求められがちです。
さらに、日本企業は社員を容易には解雇できない構造であるため、「静かな退職」をしたとしても、会社側が明確に対応することは難しいのが実情です。
このように、日本における「静かな退職」は、“ルール違反”ではないものの、“空気違反”として周囲の不満を買いやすい側面があると感じました。
たしかに、「静かな退職」は個人にとってのサステナブルな働き方であり、自分の人生を守る手段にもなり得ます。ただし、周囲とのバランスを欠いた実践は、自分の静かな退職の影で、誰かの「静かな燃え尽き」を引き起こすリスクもあるのではないでしょうか。
自分の「静かな退職」によって割を食うことになった「他の誰かの静かな燃え尽き」を生んでしまったらやるせないですからね。
だからこそ、「静かな退職」は単なる“逃げ”ではなく、構造的な働き方の問い直しのきっかけとして捉える必要があります。個人レベルで社会全体の構造を変えることは難しいかもしれませんが、自分の働き方をどう整えていくか、その視点を持つことが第一歩になるのではないでしょうか。
まとめ:自分の“働き方の主導権”を取り戻す一冊
『静かな退職という働き方』は、
- 働き方に違和感を抱えている人
- 心身が限界に近づいている人
- “頑張る”以外の選択肢を探している人
におすすめの一冊です。
ただ楽をするためではなく、持続可能に働き続けるための戦略を学べます!
📘 書籍情報
書名:静かな退職という働き方
著者:海老原嗣生
出版社:PHP新書
発売日:2025年2月28日
価格:1,210円(税込)/208ページ
最後までお読みいただきありがとうございました。
働き方に悩んでいる方の背中を、少しでもそっと押せたら嬉しいです。
それでは、また次回お会いしましょう!