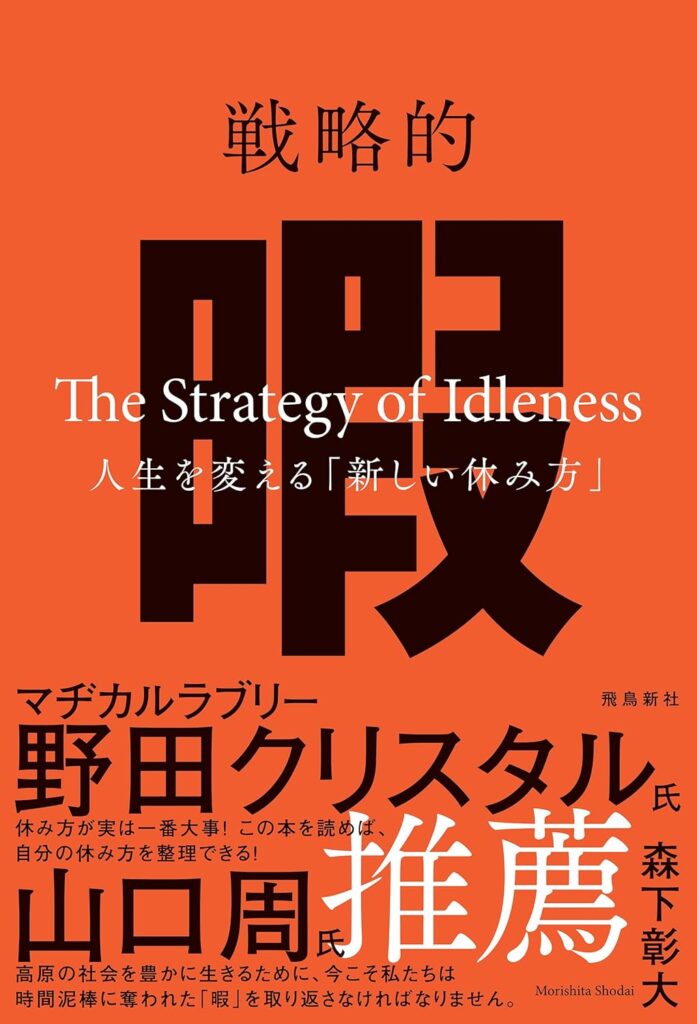こんにちは、あるいはこんばんは。ぽめおです。
今回は、森下彰大さん著『戦略的“暇”』を紹介します。
銀行員として働きながら発信や副業への挑戦をしている中で、僕はずっと「時間は作るものだ」という感覚を持っていました。一方で、単に「暇=休む」では解決しない疲れや創造力の枯渇を感じる場面も多く、どうしても「質の良い休み方」を学びたかった。そんなときに手に取ったのが森下彰大さんの『戦略的“暇”』です。
本書は単なる「休暇のすすめ」ではなく、日常に良質な余白を意図的に取り入れ、個人のエネルギーを再充填して社会にも好影響を波及させる――そんな考え方を、実証研究や文化史の知見を交えて示してくれます。読み終えて、「あ、これは今日から試せる」と感じた具体策が多かったのが決め手でした。
いつも通り、本書の結論から。
結論:良質な“暇”を戦略的に設計することこそ、創造性・回復力・幸福を生み出す最大の投資である
つまり「暇」は消極的なものではなく、能動的に設計する“戦略”であり、創造や共感、回復のための重要なインプットである――ということです。
我々は、積極的に”暇”になりにいかなければなりません。
その方法をぜひ一緒に学んでいきましょう!
目次
What:戦略的“暇”とは何か?
森下さんが語る“暇”は、単に“何もしない時間”ではありません。
それは 「意図をもって設計された余白」 であり、疲れを癒すと同時に、新しい発想や人とのつながりを生み出す源泉です。
著者は、現代人が陥りがちな「なんとなくの暇」と「戦略的な暇」を明確に区別しています。
なんとなくの暇:SNSをダラダラ見たり、テレビをBGMに過ごす時間。
→ 休んでいるつもりでも脳は情報処理に追われ、むしろ疲労が蓄積する。
戦略的な暇:スマホを離れ、自然や人間関係、身体感覚に意識を向ける時間。
→ 脳のDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)が働き、発想や自己省察が生まれる。
「暇は“空白”ではなく、“創造のための余白”である」
たとえば、古代ギリシャでは“学校(schole)”という言葉が“暇”を語源に持っていました。つまり学びや創造は余白から始まるという考え方が、歴史的にもあったわけです。
森下さんはこれを現代に引き直し、戦略的“暇”=「感覚と精神を回復させ、次の行動のエネルギーを蓄える時間」 と定義します。
そのための手段として、本書では「自然に出る」「儀式を持つ」「フィクションに浸る」「仲間と語らう」など具体的なアプローチが提案されています。
Why:なぜ戦略的に“暇”を作ることが重要なのか?
では、なぜ今「戦略的な暇」がこれほど必要とされているのでしょうか?
いくつか理由を紹介していきます。
① 注意資源(アテンション)の奪い合いが激化しているから
現代社会は“アテンション・エコノミー”と言われます。SNSやアプリの通知、YouTubeのおすすめ動画…。常に何かが僕たちの注意を奪いにきます。
これにより、脳は常に“外部刺激の処理”に追われ、休まる暇がなくなっているのです。
「脳は情報処理をやめた瞬間にこそ、創造性と自己省察のネットワークを働かせる」
つまり、余白がない限り、アイデアも気づきも生まれません。
② スマホによる“偽の暇”が疲労を深めるから
多くの人は「暇=スマホを触る時間」になりがちです。
ですが実際には、これは暇ではなく“別の刺激”です。
脳科学の実験でも、自然の中でデジタルデバイスを手放すと、創造性テストのスコアが約50%向上したという結果が出ています。
つまり、「本当の暇」はむしろ“何もしていないと感じる瞬間”にこそ宿るのです。
③ ストレス社会で「質の低い暇」では回復できないから
現代は仕事・家庭・社会のあらゆるストレスに囲まれています。そのため、ただ横になるだけの“受動的な暇”では回復効果が薄く、逆に「自己嫌悪」に陥る場合すらあります。
「戦略的に設計された暇は、ストレス耐性を高め、心身を持続的に整える投資になる」
と森下さんは強調します。
④ 歴史的・文化的にも「暇」は創造の源泉だったから
歴史を振り返ると、暇は常に創造や革新の始まりでした。
古代ギリシャの哲学も、江戸時代の文人文化も、余白の時間から生まれています。こうした事例は、戦略的暇が“贅沢”ではなく“必須の基盤”であることを示しています。
⑤ 「質のある暇」が未来を変えるから
ただ休むだけでは未来は変わりません。
しかし、質のある暇は「気づき」「省察」「仲間との関係性」を育み、次のアクションに直結します。
森下さんはこの点を、次のようにまとめています。
「暇は個人を回復させるだけでなく、そのエネルギーが周囲へと伝播し、社会全体を良い方向に変える可能性を持っている」
つまり「暇」は怠けの時間ではなく、未来をつくるための戦略的投資だということですね!
How:どのように戦略的“暇”を生み出すか
ここからは「ぽめお的に今日から試せる」アクションを具体的に紹介します。
A. デジタルデトックスを小さく始める(まずは“三上”から)
「三上(馬上・枕上・厠上)」――アイデアが浮かびやすい場からスマホを排除するだけで、脳にアイデアの着陸スペースが戻ってくる。
実践例
- 就寝30分前はノーデバイス
- 通勤中の一部区間はスマホを見ない
- トイレ・お風呂は“考える時間”にする
B. 週1回の「スローデー」をスケジュール化する(スぺパ導入)
森下さんが提案する「スぺパ」の個人版アプローチ(自然に出る/儀式空間を作る/フィクションに浸る/リアルで会う)を取り入れる。
実践例
- 土曜の朝2時間を「スローメディア読書+散歩」に当てる
- スマホはオフにして五感を使う体験に集中してみる
C. 小さな「儀式」を毎日のルーティンに組み込む
良質な暇は「偶然」ではなく「儀式」が支える。
実践例
- 毎朝のコーヒー5分は“観察の時間”にする(スマホ見ない)
- 日次ジャーナルを3行だけ書く(気づき・感謝・直近の小さな問い)
D. HPA系と内受容感覚を鍛える(ストレス耐性の向上)
戦略的暇の対処法は二つ――①内受容感覚を鍛える、②余計なストレッサーを排除する。
実践例
- 呼吸法(4秒吸って4秒吐く)を1日2回
- 週1回の「ボディスキャン」10分
- 夜20時以降は通知をオフにする
E. “不便益”を意識して体験をデザインする
効率化は目的ではなく手段。「不便益」を取り入れることで深い体験を獲得できる。
実践例
- 通勤の一部を徒歩にする
- レシピを見ずに料理してみる
- 不便をあえて残して観察する
ぽめお的感想
金融や資産形成の話をしていると「時間は金で買えばいい」と考えがちです。
でも本書を読み、「時間の質=投資の質」という感覚が腑に落ちました。
お金で買える便利さは短期には効くが、創造力や幸福は“戦略的に作られた暇”から生まれる。
僕自身がこれから取り組みたいのは以下の3つです。
1.枕上ノーデバイス(毎晩「三上」ルールを守る)
2.週1のスローデーを3か月続ける(自然散歩+スローメディア)
3.毎朝3行ジャーナルを3か月続ける(創造性の記録)
最後に――もしあなたが「時間は足りない」と感じているなら、まずは“5分の縦割り”から始めてください。
スマホを置く5分、外を見る5分、深呼吸する5分。
小さな余白が積み重なって、やがて大きな発見をもたらします。
「時間がない!」と思っている方、ぜひ手に取って、あなた自身の「戦略的暇」を設計してみてください!